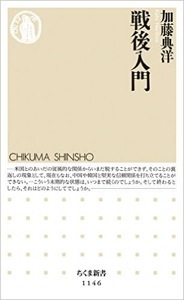8月15日

加藤典洋の『戦後入門』(ちくま新書)。新書の体裁は取っているものの635ページに及ぶ大部の本を読んでいる。休み休み読んでいて随分時間がかかり、ちょうど1945年あたりの記述を読んでいるところで8月15日を迎える事になった。原爆投下が、投下の当事者にとって、原爆の開発に関わった科学者や政治家にとって、どのような心的衝撃を起こしたかを克明に論じている。
印象に残った部分をそのまま以下に転載。
P244〜
(原爆投下以来、米国社会に現れた批判が数としてはさして多いものではなかったにもかかわらず、なぜ米国政府の指導層たちがこれほど過敏に反応したのか、、、)
その理由とは、第一に、原子爆弾の投下に対する批判と懐疑が、何より彼ら自身の出身母体である米国社会の保守層の深部、その信仰の基底部から起こってきていた事です。
米国政府の首脳周辺で、先ず最初に「懸念」を行動で示しているのは、意外なことに、ジョン・フォスター・ダレスです。ダレスといえば、反共の立場から日本の戦後の枠組みを作った事でも名高い、後に冷戦時代の国務長官として名をはせる極め付きの保守主義者です。その彼が、8月9日、米国キリスト教会連邦協議会会長の主教を先導するかたちで、トルーマン大統領を直接訪問しているのです。彼は、長老派教会の牧師の家に生まれ、当時、同派平信徒の代表的な存在でした。
続いて戦争が終わると、同じくキリスト教の他の宗派の代表からも、続々と深刻な憂慮が表明されるようになります。「我々アメリカ合衆国民はキリスト教社会として、その道徳律に対して、いまだかつてなかったほどの激しい打撃を受けた」とカトリック教の雑誌の編集長が9月号に述べ、罪に良心の呵責が伴わなければ、それは「犯罪」と呼ばれるが、「合衆国政府がとった行動は文明社会の根幹をなす情のすべて、罪の自覚のすべてをことごとく無視するものだ」と断言します。
もう一つのカトリック教会を代表する雑誌の9月1日号も、原爆投下に先立ち日本が「降伏の準備」を進めていた事実を取りあげ、批判の声をあげます。
プロテスタント派も、例外ではありません。ある雑誌の論説が、原爆の使用により「わが国は道義上弁護の余地のない立場に立たされた」と述べ、続いて、米国キリスト教の代表的神学者として甚大な影響力をもつラインホルド・ニーバーがこう書きます。
我が国のより冷静で思慮深い階層にとって、日 本に対する勝利は奇妙な胸騒ぎと不満を残すものだ。これには多くの理由があるが、最も顕著なものは、この勝利が原爆の使用によって確保された、あるいは少なくとも早められたということだ。・・・我々は日本が我々に対して使用したものよりも恐ろしい武器を彼らに使ったのだ。(「我々の日本との関係」『クリスチャニティ&クライシス』1945年9月17日号)
考えてみましょう。マッカーサーが厚木飛行場に降り立つのが8月30日のことです。このとき、日本は敗戦を受け入れ、まったく茫然自失の状況にありました。ちょうどその頃、米国に起っていたのは、このような戦争と原爆の登場に対する大衆的な昂揚と、それと裏腹の、一部の「より冷静で思慮深い階層」における、深刻な動揺だったのです。
以上転載
加えて、保守、リベラル双方からも原爆投下に懐疑と批判がわき起こっていた。これらを一掃するために、ジェームス・コナントは政府関係者、知人に呼びかけ、独自に政府に働きかけて作業チームを作り、4ヶ月をかけ、これらを一掃する効果的な一撃を準備する。それが1947年2月大部数の雑誌『ハーパーズ』に掲載された「The Decision to Use the Bomb(原爆使用の決断)」だ。これが「原爆は100万以上の米兵の命を救った」「熟慮の上の計画的な破壊」だった、という米国政府の公式見解である「原爆神話」をつくることになる。
2016年8月15日月曜日