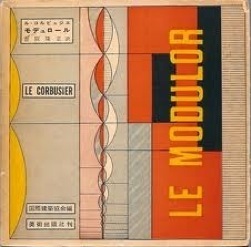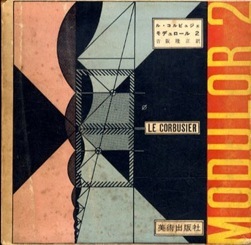モデュロール

ル・コルビュジエは「モデュロール①」1948の冒頭で次のように記している。「我々の文明はまだ音楽の完成しただけの段階に至っていないことが意識されているだろうか?」
ピタゴラスからバッハを経由して現代に至るまで、「耳」と「数」を用いて音楽を築く方法=調律法と記譜法とを道具として音楽が偉大な発展をなし遂げてきたことに、建築は到底及んでいないとの自覚が、彼にモデュロールをつくらせることになる。そして「モデュロール②」1954の巻末では、知れば知る程遠ざかって行く比例(=黄金比)の神秘の前に立ち尽くす自らの姿を曝け出している。
「私は心のなかでは音楽家であるが、実際的にはちっともそうでない。」
モデュロールは、翻訳者の吉阪隆正が「黄金尺」と訳しているように、黄金比の人体寸法への応用である。設計するための具体的な「黄金ものさし」をつくり、それを設計に使うことを目標にしているが、彼が2冊の本で延々検証しているのは結局「人体も黄金比でできている」ことにつきる。
黄金比は全ての被造物、森羅万象に潜み、あらゆるスケール(素粒子から宇宙まで)を貫く摂理であるとする畏れが、彼に人体寸法の比例関係を研究させた。結論は最初から不動の真理として先在した。
Εν αρχη ην ο λογοs.
(はじめに言葉があった。ヨハネ1:1)
ここで「言葉」と訳されている λογοs には、「比例」という意味もある。
2012年2月3日金曜日