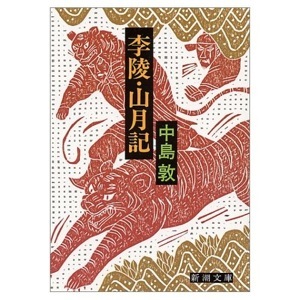皆既月食

快晴。見上げれば暗い月だけでなく、南の空にはオリオンが構え、ベテルギウス/シリウス/プロキオンの大三角形が明るく瞬いている。地動説のこの時代に夜空を仰ぎ、此方と彼方の距離や位置感覚を頭の中で味わうのは、やたらとでかい、長さ10万kmぐらいのラケットを使い、星をボールにして球技をしているような楽しい感覚なのだろうか。近眼かつ老眼でスペースシャトルに乗ったことも無い、いまだに天動説のボクの肉眼に、夜空は2次元的な漆黒の天空に貼付いた、地球から等距離に分布する点光源と見える。天動説時代に月食のメカニズムはどう説明されていたのだろう。
闇にちりばめられた星の配列に特別な意味と調和を見出そうとしたものたちの気分が、皆既状態になった月食を眺めているとわかるような気がする。ある側面は魔術や占星術と呼ばれもしたが、それらは単なるデタラメではなく、世界認識の方法そのものであっただろう。地動説を知ったからといって、宇宙の神秘が解けた訳ではない。
宇宙の法則を数学的に記述しつくそうとするイスラム/ヨーロッパの歴史と対照的に東洋では、夜空は美意識発露の手がかりとなる。
牀前看月光/疑是地上霜/挙頭望山月/低頭思故郷
李白も好きだが、中島敦の山月記「隴西の李徴は博学才穎、天宝の末年、若くして名を虎榜に連ね、ついで江南尉に補せられたが、性、狷介、自ら恃むところ頗る厚く、賤吏に甘んずるを潔しとしなかった。・・・」もすばらしい。
どちらも、カラカラに乾き硬質で冷たい光を放つ大陸の月である。日本の月は群雲が出てきたり、朧月夜だったり、水を連想させる柔らかい月だ。いずれにしても宇宙の神秘の真実は、こうした文学的表現の中に潜んでいる、と言い切ってしまおう。皆既月食、狂気の夜だから。
2011年12月10日土曜日