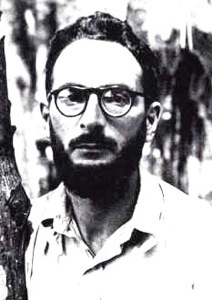建築人類学

建築と文化人類学の交差点。
ワセオケにいた時に大変お世話になった菊地靖教授。右も左も判らない我々の、一ヶ月半に渡るヨーロッパの演奏旅行に、顧問として同行してくださった。特に東欧諸国では、食事の出し惜しみをしていた食堂と渡り合って「正しいタンパク質付きの食事」を確保して下さり、命の恩人と言っても過言ではない。ありがとうございました。
菊地先生の専門は、文化人類学。
ある日、その菊地先生から電話があり、「『建築人類学』を研究する教え子が、建築の設計実務をしたいようだから、君のトコどうですか?」命の恩人の申し出、「かしこかしこまりましてかしこ」。
優秀なマキノ君は建築人類学というジャンルに斬り込み、早稲田の学生が頂くことのできる最高の名誉「小野梓賞」を受賞している。
「文化人類学」は、果てしなく広大な学問・研究領域なので、「建築」がどの辺と同じ平面上にあるのかを整理する必要がある。原広司はフィールドワークでその地平を目指した。別の手法もあるだろう。
レヴィ=ストロースは100歳だけど文化人類学は未だ新しい学問だ。面白くなりそうな予感。
(写真はマキノ君ではありません)
2009年10月29日木曜日